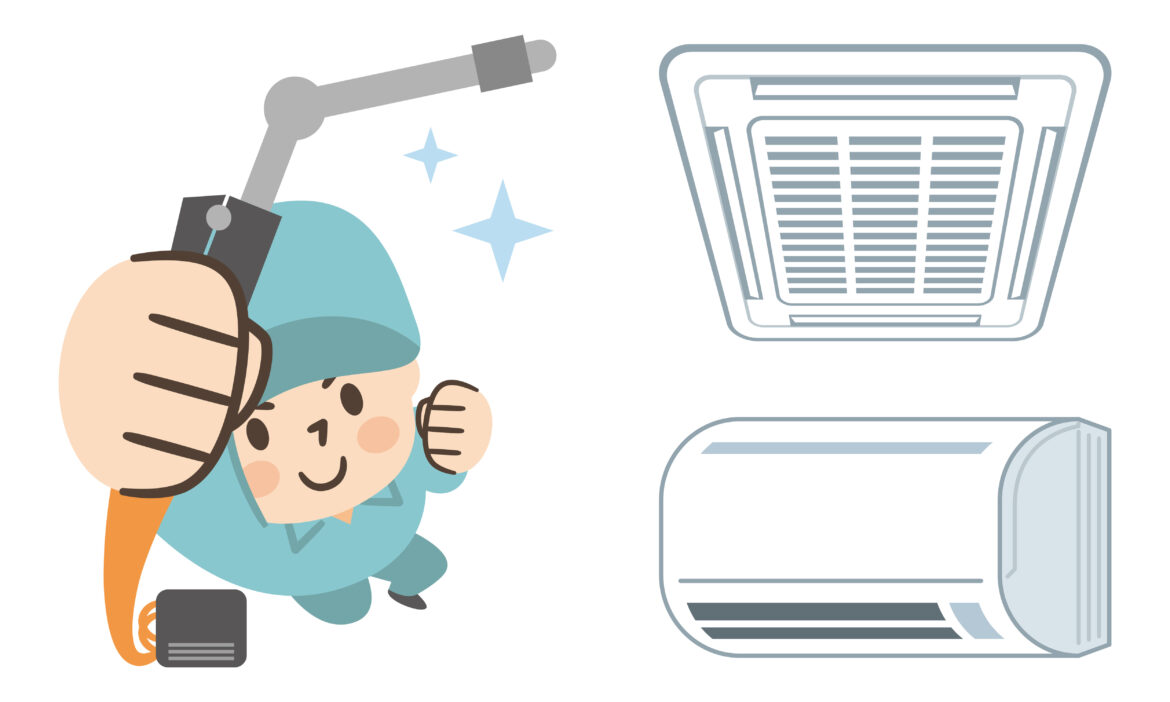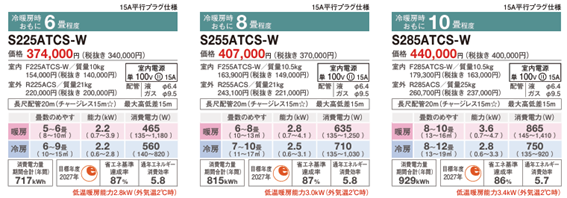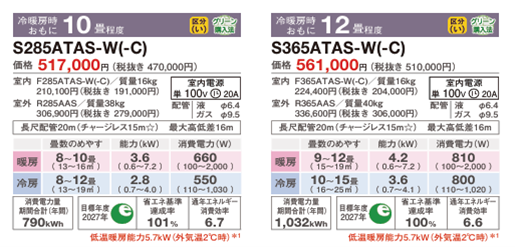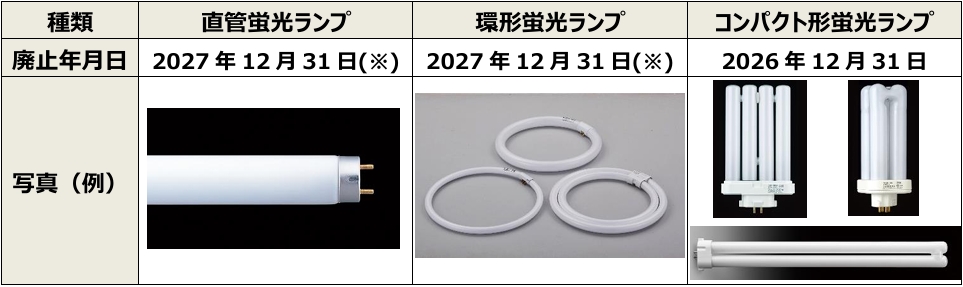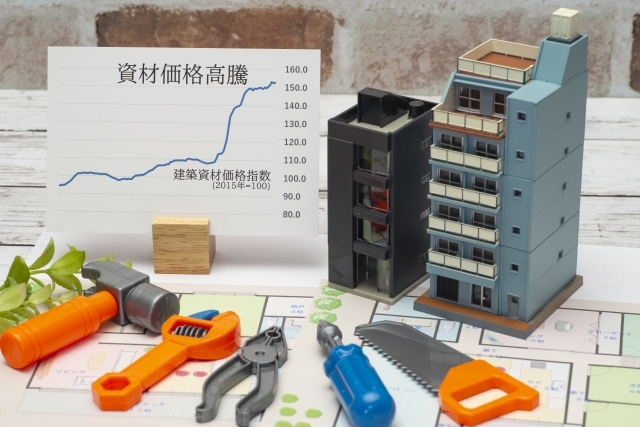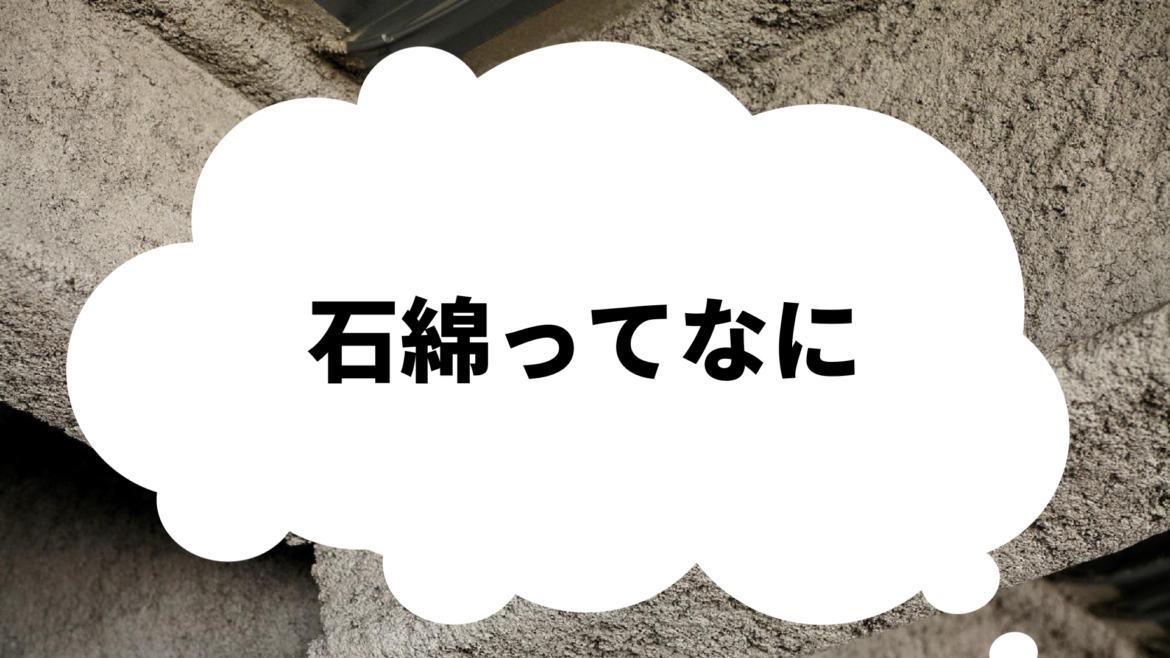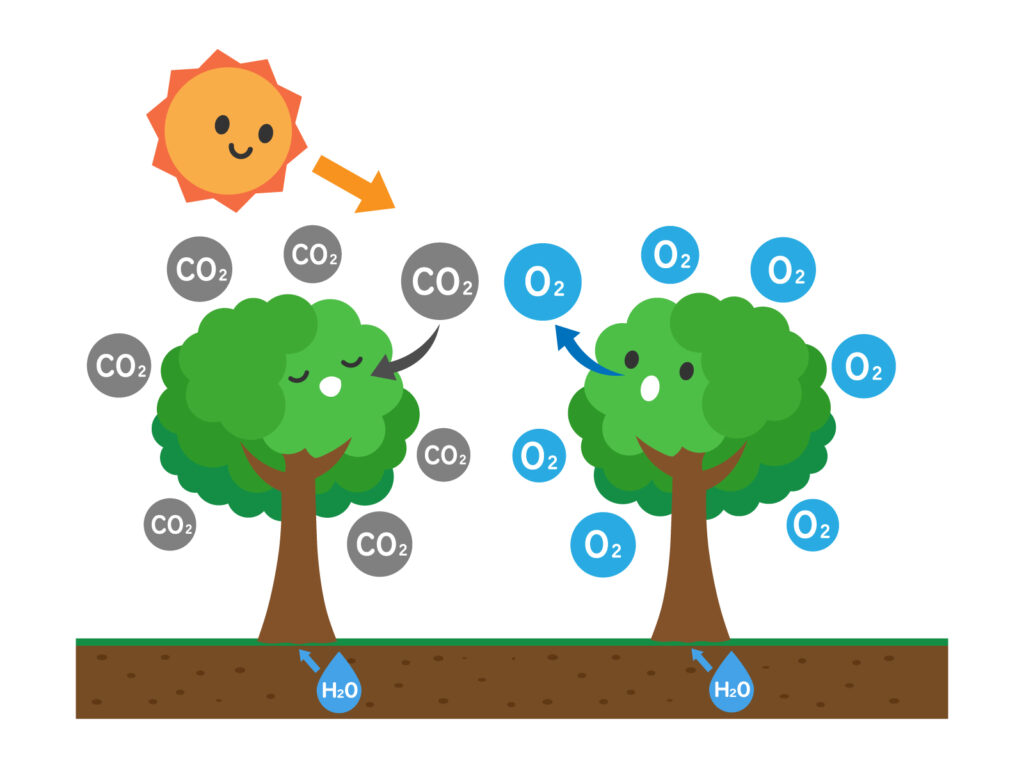空き家は、防犯上の問題を引き起こします。
その第一は不法侵入のリスクです。空き家は留守であることが明白で、防犯対策が十分ではありません。万が一解錠されてしまっても気付く人がいないため、空き巣のターゲットになりやすいと言えます。無施錠や壊れた窓から侵入され、放火の対象となる場合もあります。
長期間放置されている空き家は、不法占拠される可能性があります。不法占拠者が住み着くと、退去させるのに法律上の手続きが必要になり、所有者が大きな負担を抱える事になるとはあまり知られていません。また、犯罪の拠点とされてしまうリスクもあります。
空き家が増えることで、人目が届きにくいエリアが生まれ、地域全体の治安低下を引き起こし、防犯環境が悪化することが懸念されます。例えば子どもたちが空き家を遊び場にしてしまい、犯罪に巻き込まれたり、建物の崩壊や転落などの事故に遭ってしまうことも心配されます。
このように、空き家は不法侵入や犯罪の拠点、放火、地域の治安悪化など、防犯上多くのリスクを引き起こします。また、空き家が放置されることで事故や衛生問題、地域コミュニティの弱体化につながります。これらのリスクを軽減するためには、住宅の所有者が空き家の管理をしっかり行っていくことが不可欠ですが、同時に地域住民や行政、警察が連携して対策を講じることが重要です。